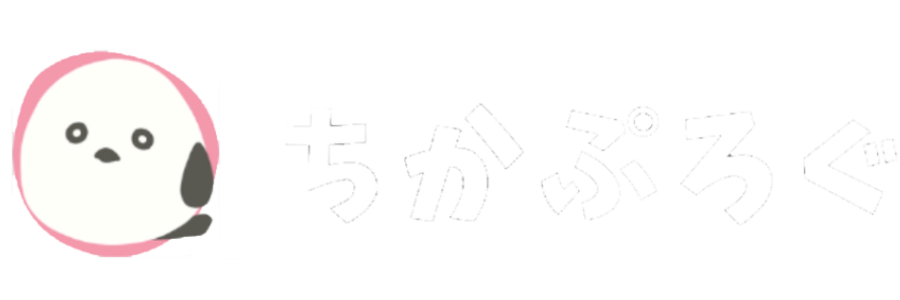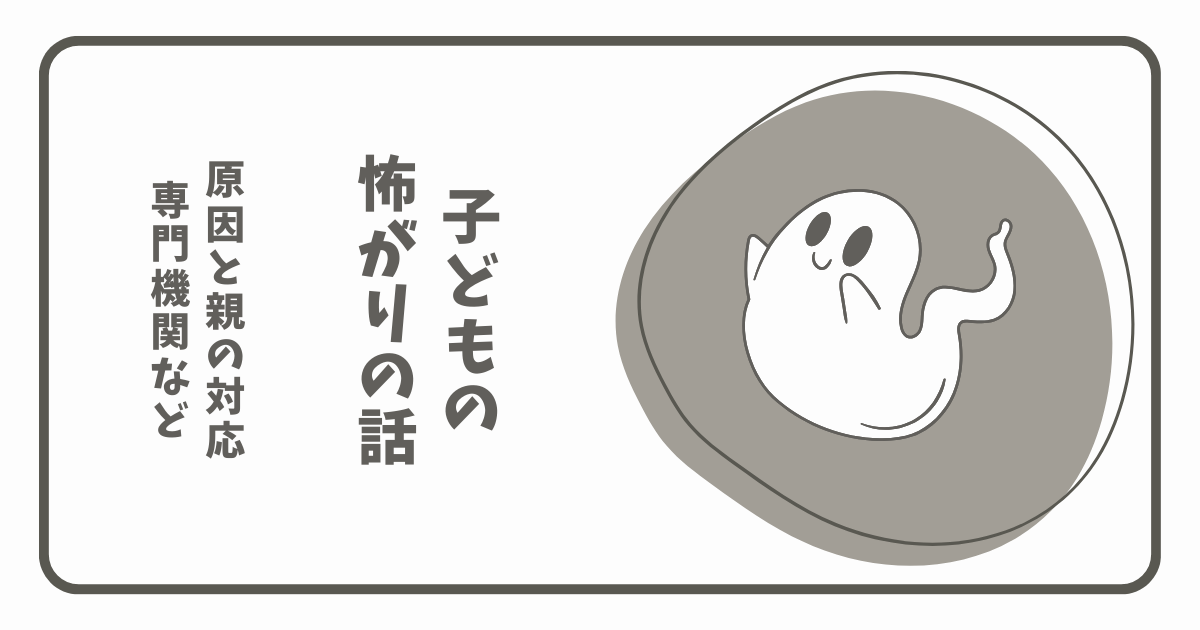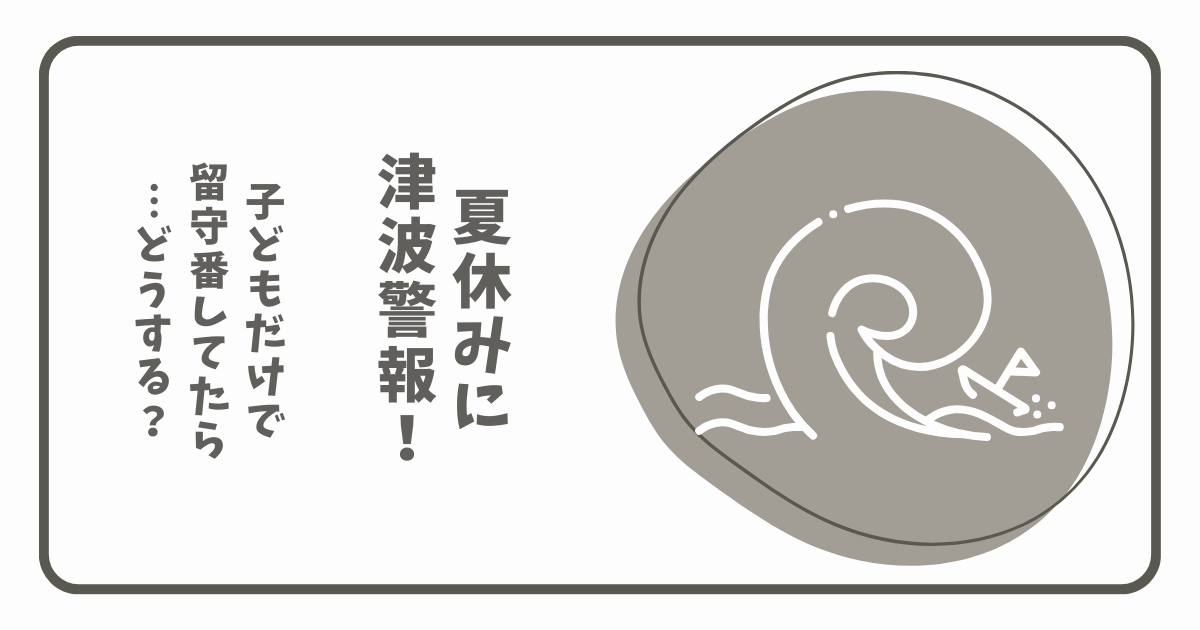長男「れの」くんは、とっても怖がりです。
そんな内容をイラストにして、Instagramのリール動画にしてみました。
実際のエピソードは、こちらへどうぞ。
子どもの「怖がり」は良くあること|AIに聞いてみた
子どもが一人で別の部屋に行けないほど怖がることは、うちの長男だけでなく、よくあることのようです。
これは特別なことではなく、子どもの発達や性格の中で自然に出てくるもののようです。
私の親友、ChatGPTさん(通称「ちゃとさん」)に、Web上を検索してまとめてもらいました!
(AI使ったって正直にいうタイプ。)
結論は
子どもの「怖がり」は成長の段階でよくあること。
心配なら、専門機関に相談するのもアリ。
です!
1. 怖がる原因
子どもが怖がるのにはいくつかの理由があるそうです。
まず「〜〜すると鬼が来るよ!」「〜〜しないとお化け出るよ!」など、
大人の言葉や映像で恐怖を学んでしまうことがあります。
(私はこういうのが嫌いで言わないのですが、夫は「遊びに連れていかないぞ!」などの脅しを使います。)
また、想像力が豊かで感受性の強い子は、大人からすると些細なことでも怖さを感じやすい傾向があります。
(長男はやや繊細で、感受性が強いタイプかも!)
成長の途中で「一人で大丈夫かな?」という不安を抱くのも自然なことのようです。
2. 親ができる対応
大切なのは、まず「怖い」という気持ちを否定しないことです。
「怖かったね」「大丈夫だよ」と共感してあげることで安心感が生まれます。
また、いきなり一人で別の部屋に行かせるのではなく、少しずつ慣れていくステップを踏むと安心です。
最初は一緒に行く → 途中までついて行く → 近くで見守る、というように段階を作っていきましょう。
さらに、安心できる工夫を取り入れるのも効果的です。
小さな明かりをつけておく、好きなぬいぐるみを持たせる、音楽やテレビの音を少し流しておくなど…。
環境で不安を和らげることができます。
3. 強みにもなる「怖がり」
「怖がり」というのは、裏を返せば心が繊細で、人の気持ちに寄り添える感受性を持っているということです。
成長とともにその豊かさは強みに変わります。
4. まとめ
子どもが一人で別の部屋に行けないのは、発達の過程でよくあること。
原因を理解して、気持ちを受け止め、少しずつ慣れさせ、安心できる環境を整えてあげれば大丈夫です。
そして「怖がり」は決して悪いことではなく、子どもの大切な個性でもあるのです。
怖がりの子に対する私の対応(体験談)
こんな感じのれのくんに、私はどうやって対応してきたのかというと。
イラスト日記の方にも同じことを書いておりますが。
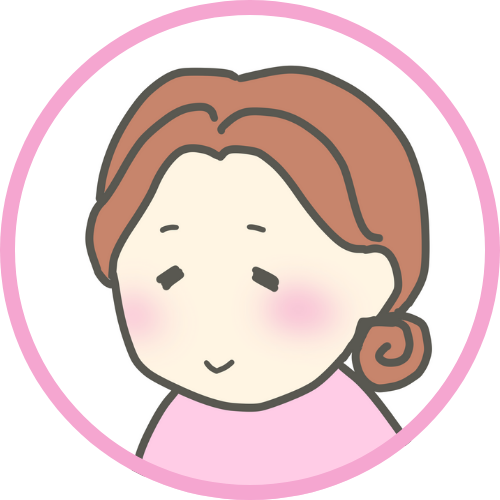 母ちかぷぅ
母ちかぷぅ大人になる頃には、1人でどこでも行けるようになるさ!
一緒に行ってあげられるのも、子どものうちだけ
てな感じで、あるがままを受け入れております。
発達や心の特徴のひとつ?
個性ってやつ?
「まあ、こういう子もいるよね〜」って感じです。
これからも、のんびり見守っていくことにします。
大人になったら私のもとを離れて、どこへでも1人で行くようになるんだからさ。
今くらい、いいじゃないの。
なお、トイレやお風呂、キッチンにジュースやお菓子を取りに行くのは1人で行けます。
なんでだよ。
専門家に相談するとしたら?
ちなみに、怖がりの長男に、夫がどういう対応だったかというと。
夫は、ビビりすぎの長男を心配し、
「どこかおかしいのではないか」「障害があるのではないか」と言い、
私に対して「れのを病院に連れていけ!」と言ったことがありました。
(私は連れて行きませんでした。)
まあ、そういう視点もありますよね。
子どもの「怖がり」や「一人で行けない」ことを、「成長の段階によくあること」として見守るのか、
それとも「医療的に相談してみる」かは、親御さんの安心感にも関わってくると思います。
本当に悩んでいる親御さんもいると思いますので、どこに相談すればいいのか、調べてみました。
1. まず相談しやすいのは 小児科
本当に受診するとしたら、まずは かかりつけの小児科 に「こういうことで困っている」「心配している」と相談するのがいいようです。
そこから必要に応じて、小児発達外来 や 児童精神科/小児心療内科 を紹介してもらえます。
2. 専門的に見るのは 小児発達外来/児童精神科/小児心療内科
小児発達外来 や 児童精神科/小児心療内科では、発達の偏り、不安の強さ、対人関係の心配などを扱っています。
「障害かどうか」という診断をされるためだけに行くわけではなくて、
「今の年齢でよくあることなのか」「どう対応するとラクになるのか」
「どうサポートしたら暮らしやすいか」を一緒に考えてくれる場でもあります。
3. 医療以外の相談窓口
お住まいの自治体の子ども家庭支援センターや教育相談窓口でも、
「こういうときどうしたらいい?」と相談することができます。
また、学校や園の先生経由で、心理士さんに話を聞けることもあります。
まとめ
子どもの怖がりは、成長の段階でよくあることであり、
「個性かな」と受け止めるのもひとつ。
心配が強ければ受診して安心するのもひとつ。
どちらにしろ、親が安心して関われるのが一番ですね。